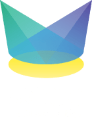NEWS
What is a MOOC ?
大規模公開オンライン講座 ( MOOC = Massive Open Online Course ) は、オンラインで誰でも無償で利用できるコースを提供するサービスで、希望する修了者は有料で修了証を取得できます。世界トップクラスの大学・機関によってさまざまなコースが提供されています。「Coursera(コーセラ)」「eDX(エデックス)」への登録者数合計は1億3千万人以上に達しており、MOOCを利用した世界規模の高等教育プラットフォームが形成されています。
Featured Courses
Four Facets of Contemporary Japanese Architecture: Technology
これは、「現代日本建築の 4 つの位相」シリーズの 2 番目のコースで、テクノロジーに焦点を当てています。 「テクノロジー」のコースでは、建築の概念化と制作を調査するための手段として、伝統工芸に使用される技術から計算のプロセスまで、テクノロジーの使用を探求した建築家の作品に焦点を当てます。 安藤忠雄氏、坂茂氏、千葉学氏、隈研吾氏、難波和彦氏、小渕裕介氏がそれぞれの建物を訪れ、それぞれの作品に込められた想いを語ります。
Contemporary Japanese Society: What Has Been Happening Behind Demographic Change?
このコースの主な目的は、現代の日本社会がどのように階層化されてきたかを、人口統計学的、家族社会学的、社会経済的観点から構造の変化を概観することです。 日本で起こった変化の具体的な内容を説明するために、基本的な統計が提示されます。 このコースを受講することによって、学習者の皆さんは、人口の高齢化、仕事や家庭における男女格差、社会経済的不平等などの社会問題に関して、各国間の類似点と相違点を確認することができるでしょう。
Contemporary Garden City Concept from Asia
大学院工学系研究科教授 横張真先生を中心とした緑・農・住のまちづくりを研究されている先生方によるこの講義は、都市計画、土地利用計画、緑地計画を、日本・アジアの視点と欧米の視点を比較しながら考察するスタイルで展開されていきます。 欧米の合理性だけを求める考え方が必ずしも「合理的」なわけではなく、日本のまちづくりのように、曖昧さを許す発想が時にはレジリエンスを高めることもあると言われており、日本固有のまちづくりの視点、理論、実践を世界に発信しています。 常時開講の形式で日本語と英語で配信しており、どなたでもCourseraから受講していただくことができます。
Interactive Computer Graphics
コンピュータ グラフィックスは、視覚的な問題解決をサポートする強力なツールです。また、コンピュータグラフィックスが持つインタラクティブ性は、ユーザーの創造性を活性化させる重要な特徴でもあります。このコースでは、コンピュータ グラフィックスの研究分野で開発されたさまざまなインタラクティブツールを、その設計原理とアルゴリズムとともに紹介します。 具体事例として、グラフィカル ユーザー インターフェイス、2D 図面および 3D アニメーション用のオーサリングツール、機能強化されたインタラクティブなコンピューター支援設計システムが話題に含まれています。 豊富なライブデモンストレーションとアサインされた課題をこなすことによって、あなた自身がもつ課題に対してどのようなツールを設計し実装すればよいか考えていきましょう。
推し授業アンケート
皆さんが「世界に発信すると面白いと思う東大の授業」について、ご意見を募集しております。下記のリンクから、あなたが「世界に発信するならこれだ!」と思う授業を是非、エントリーしてください。皆さんからいただいたご回答は、MOOCの授業開発における参考情報にさせていただきます。
アンケートに答える