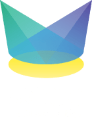Adapting to the Effects of Climate Change on Quality of Life
「伝える力を可視化する」——MOOC制作に挑んだ大学教員の想いとは
コロナ禍以後、ニューノーマルと呼ばれる社会の枠組みの一つとして、オンラインで、いつでもどこでも学べる教育コンテンツ「MOOC(Massive Open Online Course)」が再注目されるようになった。近代社会とは異なる枠組み(ニューノーマル)は、MOOCのような学びの場だけではなく、都市環境や地球環境を考えるときにも考慮されるべきこととして、人口に膾炙するようになってきている。今回は、東京大学 大学院工学系研究科 都市工学専攻の栗栖聖准教授の研究テーマ(都市サステイナビリティ学)をもとMOOC講座の制作に携わっていただいたため、お話を伺ってきた。MOOC制作に挑戦していただいた舞台裏には、研究を映像化して発信することに対する膨大な準備と深いこだわりがあった。

パワポ1枚にも妥協なし。スライドへの「美意識」
「ほんの少しのアラインメントのズレが気になるんです。」
そう語る栗栖准教授の講義資料へのこだわりは、ビジュアル情報の大切さに根ざしている。
「やっぱり、文字よりもビジュアルのほうが一瞬で情報を伝えられるんですよね。そのためのPowerPointだと思っています。文字の羅列ならワードなどの方が適していますからね。だからスライド1ページ1ページどのページも、“誰が見てもパッと分かるか”を常に意識しています。」
栗栖准教授のPower Pointに対するこだわりを感じたMOOCユニットのスタッフは、映像だけではなく、スライドも貴重な学習資源とみなし、プラットフォームであるCourseraからダウンロードできるように設定した。
MOOC制作のきっかけは「アウトリーチ」
MOOC制作のきっかけは、【テーマ4】国民の生活の質(QoL)とその基盤となるインフラ・地域産業への気候変動影響予測と適応策の検討と評価 | 気候変動影響予測・適応評価の総合的研究(S-18)というプロジェクトの一環だった。複数年計画のプロジェクトの最終のアウトプットとして、どのような発信方法がいいかを模索している中、同大学の真鍋陸太郎教授より、MOOCの制作の話が持ち掛けられたとのこと。
今までにない取り組みだったので、これまで研究成果を届けられなかった方たちにも、より分かりやすく伝えることができるのではないかということで、映像によるアウトプットを兼ねた講義制作に取り組むこととなった。
「もともと本やシンポジウムなどの発信はしていましたが、MOOCのように英語で世界へ伝える取り組みは初めてでした。研究成果を多くの人に知ってもらえる、新しいチャレンジだと思いましたね。」
苦労の連続、それでも見えた新たな発見
制作にあたっては、スクリプトの作成やインタビュー先との連絡調整、字幕チェックなどの準備作業があったという。
その準備作業の時間の捻出が特に難しかった。
通常授業の準備もしつつ、これまで行ってきたこととは違う作業の連続で想像以上に時間を要してしまった。
「リマインドを適時いただけたことで、その都度よしやろうと気を引き締めなおすことができてありがたかったです。」
また、制作を通して研究の内容をいちから見直すことができ、普段から行っている授業に対する気づきもあったという。
より、詳細にかつ、かみ砕いた言い方を意識して、今回の講義制作には携わっていただいた。
「授業ではスライドを見せながら話すので、ある意味アドリブでいけますが、MOOCではしっかり原稿を作らないといけません。文字に起こすことで、今までの授業では不足していて、もう少し深堀して説明すべき点、よりよい言い回しがあることなど改善点に新たに気づくことができました。」
結果的に授業内容をよりよくすることができたのであれば、moocユニットとしても思わぬ副産物となった。
学生の反応と授業への活用
完成した動画は、東大の授業の中でも活用していただいている。
特にインタビュー映像など、気候変動の影響を受けるであろう様々な現場(ミカン畑、都市部の設計や都市の重量の問題、交通の脱炭素化や今後なくなるかもしれない産業など)の映像を学生に見てもらいながら、先生ご自身のコメントを重ねていく形で授業に使用している。
MOOCは講義だけでなく、上記に記した現場へのインタビューや、ワークショップなど様々な映像が織り込まれている。「MOOC動画の"講義"部分に関しては直接伝えることができます。ですが現場に足を運べない学生たちにとって、映像で“リアル”を感じてもらえるのはとても意義があることで、講義の理解度も高まります。」
今後への展望と課題
今後の課題も全体を通してみるといくつか見つかったが・・・・・・
「やはり時間が限られている中での制作だったので、どうしても細部までチェックが行き届かなかった部分はあります。できあがってから、あれもあった方がよかったかもと思うことがちょっとありました。でも、次に活かせる反省点が見えたのも収穫です」。
その課題を次回のMOOC講義制作のアップデートに活かし、積極的に取り組んでいきたいと語る。
既存のメンバーも多く参加する5年計画のプロジェクトがすぐに始まると言う。新たなプロジェクトのアウトプットとして、MOOCのような形もありだと考えているそう。
「気候変動のようなテーマは5年もすれば状況が変わってきます。だからこそ、継続的な発信とアップデートが必要だと感じています。次回のプロジェクトのまとめはまた4年後、5年後になりますが、その際にまた新たな情報提供ができればといいなと。」
学びの間口を広げる「MOOC」の可能性
最後に、MOOCという取り組みそのものについて話を伺った。
「対面で学べない人たちにも知識を届けられるのは、MOOCならではの魅力です。どんな世代、どんな場所にいる人でも“学びたい”気持ちがあれば、届くコンテンツにしていきたいですね。」
「自分たちの研究や知見を社会に還元する。」
その姿勢が形になった今回の取り組みは、多くの人にとって“新しい学びの扉”を開くきっかけの1つとなっている。
ご視聴はこちらから
https://www.coursera.org/learn/climate-change-adaptation/