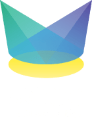Contemporary Garden City Concept from Asia ~「現場の声と風景を届けたい」
東京大学MOOC『Contemporary Garden City Concept from Asia 』の講座を中心となっておまとめいただいた横張先生に、制作過程などについてお話を伺いました。
今回、MOOC講座の制作は初めてではありませんでした。以前、サステナビリティ・サイエンスの講座制作に関わったことがあり、その経験が大いに活きました。やはり前回の蓄積があったからこそ、今回の講座は非常にスムーズに進行できたと思っています。

今後への反省点としては、私自身、カメラ映えしないタイプでカメラの前に立つのがとっても苦手なので、現地撮影ではもっと映りこまないようにした方がよかったかなと(笑)。
それはともかくも、講座をご覧いただく方がさらに深く学べるよう、今後の展開では双方向の工夫ができると良いなと思います。たとえば、ZOOMなどを用いて、年に数回程度でもいいので、実際に学んでいる学生さんと質疑応答などを通して交流ができる機会を設けることも考えてよいかと。そうした可能性が開かれているのもMOOCの良いところだと思います。
この講座の動画全体に言えることですが、やはり現場の映像や声をふんだんに取り入れているので、現場視点で見てもらえたら嬉しいです。講義だけでは伝わらない臨場感や、現場の方々のリアルな言葉があることで、より深く理解していただけるのではないかと思います。実際にさまざまな場所へ足を運んだからこそ得られた素材です。
その中でも特に印象に残っているシーンはドローンによる空撮映像ですね。これまで手軽に撮影するのが難しかった映像が、今回の講座で実現できました。練馬や西東京あたりを上空から撮影した映像をみると、市街地に囲まれた中に、これだけの農地が広がっているということが一目でわかります。この映像は、本講座以外の場面でも活用させてもらっているほどで、とても印象深いものでした。現場での撮影に幾度もお付き合いくださったクルーの皆様に、改めて御礼を申し上げたいと思います。
コースの『Contemporary Garden City Concept from Asia』という名前ですが、 「ガーデンシティ」という言葉は、20世紀初頭にイギリスのハワードが提唱した概念に由来しています。本来は都市と農地の融合(ハワードは「結婚」と表現しています)を意味するものでしたが、当時の文化的背景を基にした不動産ビジネスの影響などもあり、彼の本来の思想はなかなか正しくは伝わりませんでした。今回の講座では、そのハワードの提唱したガーデンシティの本来の意味に焦点を当てなおし、東京を中心としたアジア版として再解釈・再構築したものとして紹介しています。そういった背景から、このタイトルに決めました。
今は、都市部におけるマイクロクライメート(微気候)についてアメリカやオーストラリアの研究者とも意見交換をしています。またアジアにあっては、中国や韓国などからも講演のお声がけをいただいており、日本だけでなく世界的に共通の課題であることが実感されます。次回は、こうした海外の研究者とも連携して、このテーマを軸にした動画の制作をしてみてもいいかなと考えています。
最後に、東京の再開発にも携わっております。これまでの再開発は、老朽化した建物を取り壊し、一度更地にし、大規模な建物を新たに建てるという手法が主流でした。しかし、今ICTの普及やコロナ禍を通じてワークスタイルの急速な変化が起きているにもかかわらず、画一的な再開発が繰り返された結果、テナントの空室率が上昇するといった現象に直面しています。加えて、昨今の建設費の急騰もあり、再開発事業がそもそも成り立たないといった事態すら随所で起きています。
こうした状況に対して、私は日本の伝統的な修復技法である「金継ぎ」の発想を、都市の再開発に応用できないかと考えています。金継ぎとは、割れたり欠けたりした器を漆と金粉で修復する技術であり、そうやって修復した痕跡が、むしろ味わいや美しさの表現と解釈され、新たな価値を生み出すとされます。すべてを新しくつくり直すのではなく、傷や歴史をも受け入れ、上手に残しながら、部分的な修復によって新たな価値を生み出す——そうした考え方は、まちづくりにも応用できるはずです。
「すべてを作り変えるまちづくり」ではなく、金継ぎ的な発想のもと、必要以上にお金をかけたり資源やエネルギーを浪費したりすることなく、街の記憶や個性を活かし、新たな付加価値を創り出す、そういった「粋な」まちづくりのあり方を考えています。こんなテーマも、日本から発信する将来のプログラムとしては、おもしろいかもしれないですね。
【講座情報】Coursera: "Contemporary Garden City Concept from Asia "
https://www.coursera.org/learn/contemporary-garden-city-concept-from-asia